省エネ法に不適合となるケースが増えてくる
2024年4月、建築物省エネ法が改正され、大規模(2,000㎡以上)の非住宅の基準が強化されます。15%~25%の強化となり、不適合となる建築物が必ず増えてきます。
現行のままでは、工場の1割が不適合、事務所は3割が不適合、病院等では5割が不適合、飲食店に至っては6割が不適合となります。
省エネ基準への適合させるにはどうしたらよいか?
省エネ基準は大きく分けて、【外皮】と【一次エネルギー消費量】の2つがあります。
PAL【外皮性能基準】は非住宅の場合は省エネ基準への適合義務はありません。
BEI【一次エネルギー消費量基準】が基準となる数値以下かどうかによって判断します。
BEIの数値算出時に、外皮性能に関する数値を入力するため、結果的に外皮の性能も重要となってきます。
つまり、外皮と一次エネルギー消費量に影響する設備のそれぞれの面で対応させる方法があります。

設備性能を高くする方法

空調機
空調機は、省エネ性能への影響が比較的大きくなりやすい要素です。そのため省エネ性能の高い空調を採用すれば、基準値は良い数値となり適合しやすくなりますが、その反面コストがかかるというデメリットもあります。
また全熱交換器を入力している場合は、外気導入量の割合を求めて80%以上であることの確認も必要です。最低限の設備図面と給排気の経路に対しての理解がなく入力の誤りも比較的多い項目です。
給湯設備
評価対象の給湯設備の能力が低かったり、按分計算が必要な設備をそのまま入力して不適合となっているケースもあります。給湯器自体はそのままで、保温仕様、節湯器具を用いることによって適合することもあります。自動給湯栓、小流量吐水機構のある水栓、ロックウールやグラスウールの保温管を用いることも検討してみましょう。
按分計算をする場合、給湯経路を正確に読み取り、用途ごとの負荷も正しく算定する必要があります。
照明設備
用途により評価対象室が異なるため、評価対象室の照明設備の省エネ性能を向上させたり、設置数を減らすことにより、適合させることが可能です。人感センサー、明るさセンサー、タイマー制御の照明を導入することでも結果を向上させることできます。コスト面での調整も必要です。
太陽光発電設備
適合が難しい場合は、太陽光発電設備を導入することも検討しましょう。ただし売電がないことが条件となります。イニシャルコストは上昇するので注意が必要です。
外皮性能を高くする方法

外壁、屋根の断熱材
単純により性能の高い、断熱材を用いれば結果の数値は良くなります。それ以外に、熱伝導率や熱貫流率による数値入力を検討することでも結果の性能値を高くすることもできます。
開口部
外壁などと同様に省エネ性能高い開口部を採用すれば結果は良くなります。また熱貫流率や日射熱取得率の数値入力を検討することでも結果が上昇することがあります。単純に開口部を小さくすることでも一般的には省エネ性能があがります。
標準入力法を検討する
モデル建物法より精緻な計算方法である標準入力法の採用により適合する場合もあります。しかし外部委託費の上昇、省エネ機関への手数料上昇により採用される件数は大規模物件などでかなり限定的と言えるでしょう。
用途ごとの適合方法
用途別に考える場合、それぞれの用途において、不適合になりやすい部分があります。
工場の場合
工場は、照明のみ評価対象となっています。さらに対象となる室は倉庫などに限定しているので、適合させるには、照明で消費性能の高い物を倉庫などに対して配置すれば適合となります。
事務所の場合
用途別で考えると、事務所は、空調と照明の影響が大きい用途となります。
用途単位で考える場合は、省エネ性能の高い、エアコン、照明を採用すると比較的適合しやすくなります。照明は全ての室ではなく、照明評価対象室のみで調整が可能です。
飲食店の場合
飲食店は、空調、換気、照明、給湯それぞれ基準に超えてしまいがちです。いずれもある程度のデザイン性が必要となるためその結果省エネ性能基準に不適合になりやすい用途です。
外皮性能も高めて、太陽光発電設備を設置するなど総合的に対応していかないと不適合となることが多いため、建築主様との調整に時間がかかることが多いでしょう。

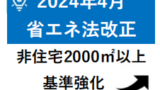


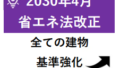
コメント